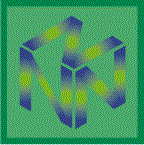
�u���̍����q�ɂ����鉻�w�����ߒ��Ƃ��̕��q���J�j�Y���v
�\���q���͊w�V�~�����[�V�������t����_�C�i�~�N�X�̒T���\
�i�����w���w�x�A�Q�O�O�O�N�W�����f�ڗ\��L���j
���É���w��w�@�l�ԏ��w������
�����E�������w��U �������_�u��
��������
���̍����q�@�|�t����_�C�i�~�N�X�̊i�D�̕���\
2000�N��̉��w��1900�N��̉��w�Ƒ傫���قȂ�_�������炭2����B���͉��w�����̎��ԕω��i�t����ߒ��j����荎���ɒNj����邱�Ƃł���A���͋��啪�q�A���ɒ`������DNA�Ȃǂ̐������ۂ̊ւ�镪�q�i���厩�R�x�n�j�̉��w������I�ɐi�W����Ƃ������ƁA�̂Q�ł���B�����I�܂Ől�Ԃ��������鎞�Ԃ̗���͒x�������B�������A���q�����w�Ȃǂ̖ڊo�����i���ɂ�荡��e���w���c�̕���\�ʼn��w�������ǔ�����悤�Ƃ��Ă���1)�B����A���ݐi�s�����Q�m���v���ɏے������悤�ɐl�ނ͍���Ō�Ɏc���ꂽ�傫�Ȑ_��ł���g�����h�ɁA�����^�[�Q�b�g���i�������Ɍ�����2)�B�{�e�ł͍��܂Ŏ��B�ɂ͎~���Č����Ă��ĕ�����Ȃ������������̉��w���ۂ�A���q�̋��傳�̂ɔ����I�ȗ�����f�O�����链�Ȃ��������w�I�Ώۂ̒�����A���ɐ������ۂɐ[���ւ�����̍����q�ɂ�����f�ߒ���I��ŁA���q���͊w(MD)�V�~�����[�V����3)�����炩�ɂ�����ŐV�̃g�s�b�N�X���R�Љ��B
��_���Y�f�����^�~�I�O���r���̌��𗣂ɔ����������_�C�i�~�N�X
�ŋ߁A�k���̓s�R�b���ԕ����A���`�X�g�[�N�X�����}�������@��p���āACO�����^�~�I�O���r���iM��CO�j��CO���𗣂̍ۂɐ�����]��G�l���M�[���A�����Ƀw������O���r������n�}�i���j�ɎU�킵�ɘa���Ă����̂����A�w���̋����}���o���h���x�̎��ԕω��𑪒肵�Ė��炩�ɂ���4)�B�Ƃ��ɖʓ��U�����[�h�ł����4�o���h�̌����ɂ́A1.9�}0.6ps(93%)�A16�}9ps(7%)�Ƃ������萔�������ɘa�ߒ��̓������邱�Ƃ����o�������A���̎����̓~�I�O���r�����ŋǏ��I�ɐ������U���G�l���M�[���o���h���ɈقȂ������萔�Ŋɘa���邱�Ƃ����������łȂ��A�P��o���h�̊ɘa�ɂ��قȂ镡���̉ߒ�����݂���Ƃ��������������Ă���B���̎��������́A���܂ł̊ϑ����u�ł͋�ʂł��Ȃ��g��u�̏o�����h�Ȃ̂ł���B�Ƃ��낪���̓���MD�V�~�����[�V�������g���ė\�����Ă����O���[�v�������B1987�N�AHenry��̓~�I�O���r���ɉ��p���X�ɑ�������^���G�l���M�[���u�ԓI�ɉ����āA���̌���G�l���M�[�ɘa�ߒ���ǐՂ��A��̎��萔�A1-4ps(50%)�A20-40ps(50%)�Ă���5)�B���͔ނ�̂��̌��������̌�̃w���̐U���G�l���M�[�ɘa�ɂ��Ă̊����Ȏ��������𑣂����̂ł������B
�`�g�N�������_���y�f�ɂ�����R�q�[�����g�����_�C�i�~�N�X
�d�q�`�B�n�͎��B�̐��������̃G�l���M�[���ł���`�s�o�i�A�f�m�V���O�����_�j�Y����傽�锽���o�H�ł���B���̍ŏI�i�K�ŏd�v�Ȗ������ʂ����Ă���̂��`�g�N�������_���y�f�ł���A���̊������ʂɂ̓w���Ɠ����q���Q���܂܂�Ă���B���̍\�����ߔN���炩�ɂ����6)�ƁAMD�V�~�����[�V������p���Ċ������ʁi�w��a3�|CuB�j�ŋN����z�ʎq�̒��������R�q�[�����g�����_�C�i�~�N�X(coherent reaction dynamics)���������ꂽ�i�}�P�j7)�BLambry��̓w���ia3�j�Ɍ�������CO�͌��𗣌�̐��Sfs�œ��iCuB�j�ւƈړ����A���̍ۃ`���V��(Tyr280)�ƃq�X�`�W��(His276)�Ƃ̊Ԃ̋��L�����̑��݂��d�v�ł��邱�Ƃ��w�E�����B�Ƃ��ɂ��̌�����CO�^�������ӊ��փJ�b�v�������ACuB�ߖT�ɑ���������炵���B�܂�CO�̍ł��d�v�ȉ^���͖�90���̉�]�ł���ACuB�̍ň��蕔�ʂւ̌�����300-400fs�Ŋ�������Ƃ��Ă���B�ŋ߁A��X��CO�����^�~�I�O���r���̌��𗣉ߒ��̕��q�@�\�ɂ����Ă��ACO�̉^�����A�]��G�l���M�[�U��ɑ傫�Ȋ֘A������炵�����Ƃ����o����8)�B���̎����̓`�g�N����c�_���y�f�ɂ�����CO�_�C�i�~�N�X�Ƃ̗ގ������璍�ڂ����B
�J���E���`���l���̃C�I�����߂̕��q�@�\
�����܂�MD�V�~�����[�V������p���Ė��炩�ɂ������w���`�����̊W����t����_�C�i�~�N�X�ɒ��ڂ��Ă����B������MD�V�~�����[�V�����͕��t��Ԃ̐��������q���x���Ŕ����I�ɗ������邽�߂ɗp�����邱�Ƃ������B1998�N��K+�`���l��(KcsA)�̌����\�������肳�ꂽ9)�̂��āA���N�ɂȂ������q���͊w���R�G�l���M�[�ۓ��@�iMD/FEP�@�j�ɂ��KcsA�ɂ������C�I�����ߌo�H(ion permeation pathway)�Ɋւ�����Ȃ��ꂽ10)�B���̌��ʁA�`���l�����ɐ��̃J���E���C�I�������݂��Ă����Ԃ�����ŁAKcsA�������C�I���`���@�\�imultiple ion
conduction mechanism�j���̗p���Ă���炵�����Ƃ𖾂炩�ɂ���(�}2)�B����ɉ\�ȓ`���o�H�ׂ�ƁA�ł�����Ȍo�H�����R�G�l���M�[�I�ɖ�5 kcal/mol�����قȂ����A��������̎�v��Ԃ̊Ԃ̑J�ڂł��邱�Ƃ��������ꂽ(�}3)�B�C�I�����ߋ@�\�ɂ������I�𐫃t�B���^�[�̋@�\���A���̎O�����I�\���ƒ��ڌ��т��Ē�ʓI�ɋc�_���ꂽ�_�������]������A����A���̐��̍����q�̋@�\�ɂ��Ă��A����������@�ɂ��𖾂��i�ނ��̂Ǝv����B
�t����_�C�i�~�N�X���𖾂���l�c�V�~�����[�V�����̑傫�ȉ\��
�{���A�`������ÏW�����n�Ȃǂ̃_�C�i�~�N�X�ɂ́A�@�֗^���鎩�R�x�̑���(�厩�R�x��)�A�A���R�x���₻�̊Ԃ̔���`���A�B�e���R�x������t���鎞�ԃX�P�[���̑傫���ꗁA�ɂ��A�t�����퐫�����ۂ̖{���ɐ[�����ђ����Ă���B�ߔN��MD�V�~�����[�V������p���������́A���������R�̓��������̓������q�̂��@�\�ɑ傫�Ȗ������ʂ����Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă����B�}�N���ȃ��x���ł̋@�\�Ɍ��т����~�N���ȃ��x���ł̔t���퐫�̗�����[�߂邽�߂ɂ́A�傫�ȕ��q�ό`���������̓����q��ÏW�n�ɂ����鉻�w�����͑ł��Ă��̃v���[�u�ł���B�����ɂ͈ꌩ�M���t��Ԃɂ݂���}�N���ȃ��x������͑z�������Ȃ��_�C�i�~�b�N�ȏ�Ԃ��~�N���ȃ��x���Ŏ������Ă���B���̂Ƃ��땪�q���͊w�V�~�����[�V�����͐��̍����q�Ȃǂ̔���`�厩�R�x�n11)��^���������舵������B��̕��@�Ȃ̂ł���B�����̎Ⴂ����҂̎Q�����肤�B
�Q�l����
�Ⴆ�A���{���w��ҁA�G�����w�����A��44���u���������w�_�C�i�~�N�X�v (�w��o�ŃZ���^�[�A2000)�B
1)�Ⴆ�A�����w���w�x(���w���l)�A2000�N4�����A���W�L���u�q�g�Q�m����ǖڑO�I�v�B
3) ���q���͊w�V�~�����[�V�����̊�b�ɂ��ẮA�Ⴆ�A����i�A�g�R���s���[�^�P�~�X�g���|�̊�b�h�A�����w���w�x(���w���l)��52��(1997�N)�̘A�ڋL���₻�̎Q�l�������Q�ƁB
4) Y. Mizutani and T. Kitagawa, Science, 278, 443 (1997).
5) a) E. R. Henry, W. A. Eaton
and R. M. Hochstrasser, Proc. Natl. Acad.
Sci. U.S.A., 83, 5367 (1986). b)
T. Lian, B. Locke, Y. Kholodenko and R. M. Hochstrasser, J. Phys. Chem., 98,
11648 (1994).
6) S. Yoshikawa, K.
Shinzawa-Itoh, R. Nakashima, R. Yaono, E. Yamashita, N. Inoue, M. Yao, M. Fei,
C. Peters Libeu, T. Mizushima, H. Yamaguchi, T. Tomizaki, T. Tsukihara, Science, 280, 1723 (1998).
7) a) U. Liebl, G. Lipowski, M.
Nėgrerie, J.-C. Lambry, J.-L. Martin and M. H. Vos, Nature, 401, 181 (1999).
b) J.-C. Lambry, M. H. Vos and J.-L. Martin, J. Phys. Chem. A, 103, 10132 (1999).
8) I. Okazaki, Y. Hara and M.
Nagaoka, submitted for publication.
9) D. A. Doyle, et al., Science, 280, 69 (1998).
10) J. ��qvist and V. Luzhkov, Nature, 404, 881 (2000).
11) ���̍����q�ȊO�ł̔���`�厩�R�x�n�̔t����_�C�i�~�N�X�̌�����A���̕����w�I�Ӌ`��֘A���Ȃǂɂ��ẮA��b�����w�������̌�����i�����E�˓c��ҁA�w���������x�A��73��
��1�� (1999)�j���Q�ƁB
�}�̐�����
�}�P�@�R�q�[�����g�|�s�����[�V�����ړ��̉^���w�ƒ�Ă��ꂽ���̃��J�j�Y���B
A)�@����Ԃɂ������z�ʃw��a3�̃|�s�����[�V�������z�B�ΐF�_�̋Ȑ��͑��u�̉������B
B)�@�������W�ɉ��������������_�C�i�~�N�X�̊ȈՃX�L�[���B50fs�ȓ��ł̗�N��ԃw��a3���̐����ɂ���āA�g�����������W�ɉ����Đi�ށB����Ԃւ̌����̈�ւ͔�������(350fs)�ɓ��B����B���ʉ߂ŁA���z��80�|90��������Ԃ֊ɘa���A�c���10�|20���͂��̌�̒ʉ߂�҂B
C)�@MD�G�l���M�[�ŏ����Ɋ�Â��Ē�Ă��ꂽ�w��a3�|CuB�ɂ�����Ή��_�C�i�~�N�X�B
�}�Q�@�n�}�aKcsA�`���l���i�S�̃T�u���j�b�g�̂���1�͍E��������悤�ɂ��邽�߂ɍ폜����Ă���j�B�@�זE�NJO���߂��̃t�B���^�[�̈�ł́A�o�Ɏq���[�����g�������i�J���{�j����Q���`12���̒����ɂ킽���čE���ɔz�����A���߂���C�I���̈��艻�������炷�B�@�t�B���^�[���̒��S��E�͑����̐����q(��30��)�����e���邱�Ƃ��ł��A�����I�ɑ���ꂽ��E�̈�ł̊g�U�d�q���x�͗n�}�a�C�I���̑��݂��������Ă���B�@�}�̍\���ł́A�Q�̐����q(�ԋ�)�A�I�𐫃t�B���^�[�ɂ�����2�̃C�I��(��)�Ɛ��Ŗ��������S��E�ł̂P�C�I��(��)��������Ă���B�@���ׂĂ̌v�Z�́A�`���l�����~���͌^�̎������ɖ��ߍ���ԂŎ��s���ꂽ�B
�}�R�@���1010(1)������0101(1)�ւ̈��^���̎��R�G�l���M�[�v���t�@�C��(���ϗ̓|�e���V����)�B�@���̃v���t�@�C���́A2��Ԃ̔z�u�̊Ԃ̋�ԗ̈�3-4����A�Q�̃t�B���^�[�C�I�����E�ɉ����悤�ȁA50�̈قȂ����ʂɑ��ĘA�����čS���������Čv�Z���ꂽ�B�@���̉ߒ��łP�̐����q���I�𐫃t�B���^�[�����E�։����o����āA�\�z�����悤�ɁA�V�������P���q�������I�ɊO������t�B���^�[�ɓ���B